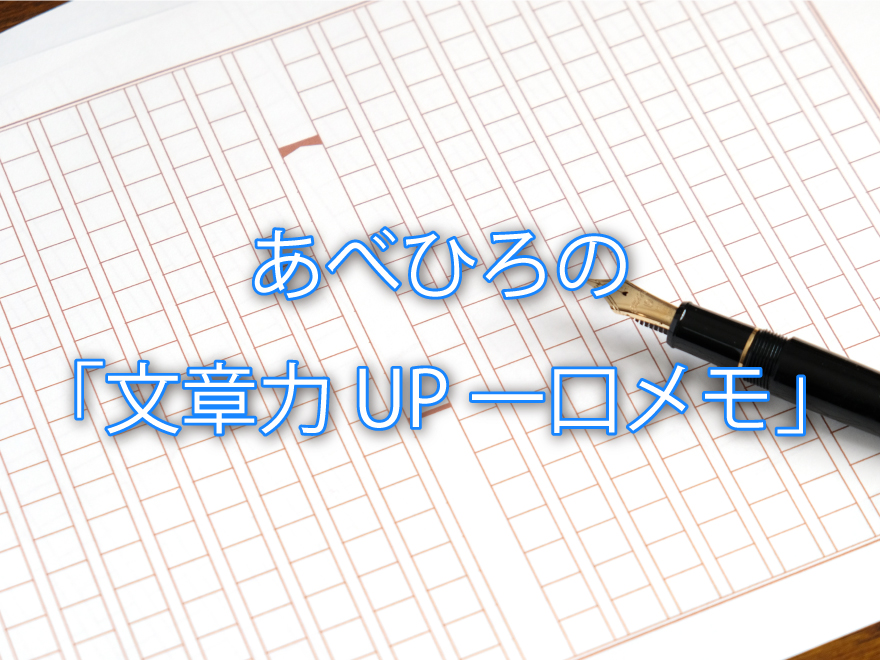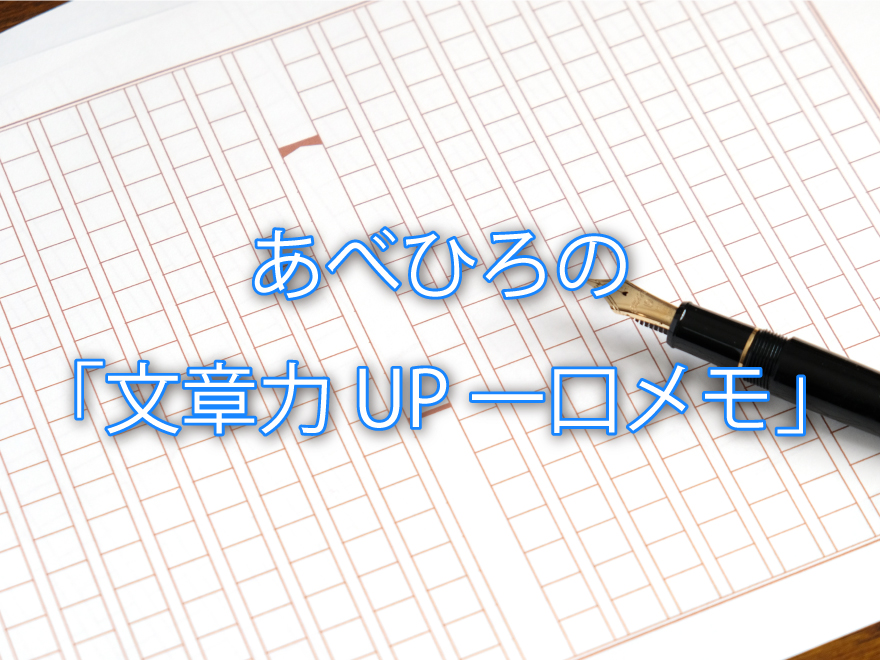| Part 1 ウォーミングアップ | 01 ある相談 |
| 02「いい文章」とは? |
| 03 文章を書く3つの喜び |
| 04 文章力の7つの要素 |
| 05「書く力」は「考える力」 |
| Part 2 受け手発想で書く | 06 読み手の側にまわってみる |
| 07 1つの改善案 |
| 08 宛先とタイトル |
| 09 箇条書きにする |
| 10 重複や無駄な言葉を省く |
| 11 丁寧に書き過ぎない |
| 12 必要な情報は書く |
| 13「ちょっと一息」半覚半睡の時が、一番創造的 |
| Part 3 文の基本形を確かめる | 14 文の基本形 |
| 15「何が(誰が)、どうした」のか |
| 16「何(誰)を(に)どうした」のか |
| 17 主語を間違えない |
| 18 主語をなるべく変えない |
| 19 述語の共用にご用心 |
| 20「ことだ」で受ける |
| 21 日本語は述語中心言語 |
| Part 4 簡潔に書く | 22 重複を省く |
| 23 無駄な言葉を削る |
| 24「と感じた」「と考えた」「と認識している」を削る |
| 25 難しい言葉で飾らない |
| 26 文頭をシンプルにする |
| 27 動詞をシンプルにする |
| 28 全体をシンプルにする |
| 29「ちょっと一息」日本語の仕組み |
| 30「ちょっと一息」英語の仕組み |
| Part 5 分かりやすく書く (1) | 31 主役を早く登場させる |
| 32 基本は時系列 |
| 33 修飾語は直前に置く |
| 34 意味の狭い言葉を使う |
| 35 見出し |
| 36 他の意味に取れる表現は避ける |
| 37「因果関係」を明確に |
| 38 曖昧接続を避ける |
| 39「結論を先に」には例外もある |
| Part 6 分かりやすく書く (2) | 40 短く言い切る |
| 41 一度にたくさんの荷物を渡さない |
| 42 主役の数だけ文を分ける |
| 43 挿入句は別の文にする |
| 44 箇条書きにする |
| 45 表にする |
| Part 7 的確に書く | 46 やさしい言葉を正しく使う |
| 47 矛盾したことは書かない |
| 48 能動と受動(受身) |
| 49「する」と「させる」 |
| 50「なる」と「する」 |
| 51 何でも「ことで」でつながない |
| Part 8 「てにをは」(助詞) | 52「に」と「で」を使い分ける |
| 53「を」ではなく「に」を使う |
| 54「に」ではなく「を」を使う |
| 55「を」と「で」、「を」と「が」を使い分ける |
| 56「ちょっと一息」「は」はスーパー助詞 |
| Part 9 「読点(、)」 | 57 長めの主語の後に |
| 58 長めの目的語の後に |
| 59 原因と結果、理由と結論の間に |
| 60「状況・場」と「そこで起きていること」の間に |
| 61 読点が欲しい場所一覧 |
| 62 読点によって意味が変わるケース(1) |
| 63 読点によって意味が変わるケース(2) |
| 64 意味の固まりを読点で分断しない |
| 65 句点は文末のみで打つ |
| 66「ちょっと一息」日本語は曖昧か |
| Part 10 共感が得られるように書く | 67 五感を使って追体験できるように書く(1) |
| 68 五感を使って追体験できるように書く(2) |
| 69 余計な前置きを書かない |
| 70 具体的なエピソードから書き始める |
| 71 修飾語、強調語を少なくする |
| 72 凝った表現を使わない |
| 73 自分のことは控えめに書く |
| 74 余計な結びも書かない |
| Part 11 長文をスッキリ構成する | 75 段落の長さと数 |
| 76 段落の骨子 |
| 77 前提となる事実を最初に書く |
| 78 同じ話はまとめて書く |
| 79「ちょっと一息」「すごく」は死んだか? |
| Part 12 視覚的効果と表記 | 80 ホワイト・スペースを活用する |
| 81 分かりやすい報告書の一つのモデル |
| 82 上記文書の原文とその問題点 |
| 83「 」を活用する |
| Part 13 話し言葉の影響を避ける | 84 無意味な飾り |
| 85「に対して」 |
| 86「自体」「自身」 |
| 87「になります」 |
| 88「いく」「くる」 |
| 89 短縮表現 |
| 90 文頭の「なので」 |
| 91「かな」「かな」「かな」 |
| 92 その他の逃げ腰表現 |
| 93 ずらした表現 |
| 94 おわりに |